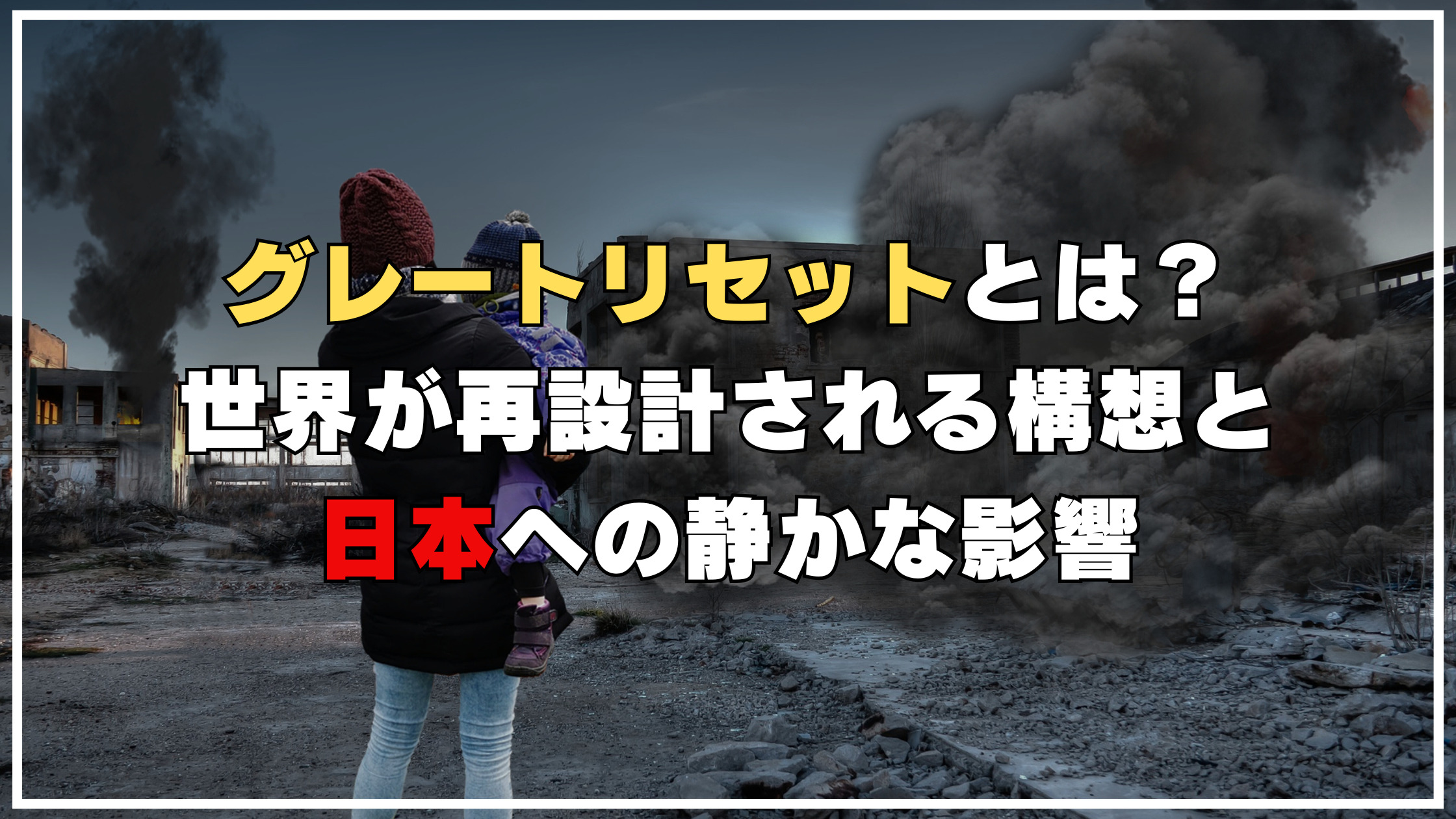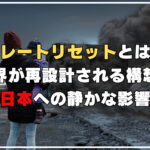あなたは「グレートリセット」という言葉を聞いたことがありますか?
世界経済フォーラム(WEF)が提唱し、一部の政治家や企業リーダーたちが賞賛するこの構想は、
パンデミック後の世界を根本から作り直す“新しい世界の設計図”とも言われています。
しかしその一方で、「自由な社会が終わる前触れ」「全体主義への移行」「個人の財産が奪われる世界」といった不安の声も急速に広まっています。
残念ながら日本では、このテーマはあまり報じられず、知っている人はごく一部です。
ですが、水道の民営化、種子法の廃止、デジタル化の加速、マイナンバーの拡張、実は私たちの生活にも、グレートリセットの影響はすでに静かに浸透し始めています。
今回の記事では、グレートリセットの公式な目的と理念から、なぜ一部で「危険視」されているのか、そして日本社会への影響までを、陰謀論に陥らず、事実に基づいてわかりやすく解説します。
知らないままでは“選べない”。だからこそ、知っておくべき構想なのです。

スポンサーリンク
第1章:グレートリセットとは?──公式の説明と背景

世界経済フォーラム(WEF)とは?
「グレートリセット(Great Reset)」は、世界経済フォーラム(World Economic Forum/WEF)が2020年に打ち出した社会改革ビジョンです。
WEFは、1971年にスイスで設立された非営利団体であり、各国首脳・中央銀行総裁・国際機関・グローバル企業のCEO・学者・財団代表など、世界中の“意思決定層”が集まる会議を主催しています。
毎年1月に開催される「ダボス会議」はその代表的なイベントで、事実上、世界の政治経済の方向性が語られる場となっています。
創設者であり議長を務めるクラウス・シュワブ氏は、著書『COVID-19: The Great Reset』の中でこの構想を次のように位置づけています。
「“COVID-19は、我々にグローバルな社会・経済システムを再設計する歴史的な機会を与えた。”」と。
グレートリセットの提唱とタイミング
グレートリセットが発表されたのは2020年6月。
それは、まさに世界がパンデミックに揺れていた最中のことでした。
このタイミングに対して、多くの人が次のような疑問を抱きました。
なぜウイルスの混乱の中で、すでに“再設計”の提案が出せるのか?
危機をチャンスに変える“準備”がすでにできていたのでは?
誰が、どの立場から“新しい世界”を設計するのか?
WEFやクラウス・シュワブ氏は、「パンデミックはシステムの欠陥をあらわにした」と主張しますが、構想のスピード感や規模の大きさに対して、一般市民の間には強い警戒感も広がっていきました。
第2章:グレートリセットの3本柱と“理想”の未来像

WEFが提唱する「グレートリセット」は、ただの経済政策ではありません。
彼らが描いているのは、資本主義・社会構造・人間の価値観そのものを変革するビジョンです。
その構想は、以下の3本柱(Three Main Components)で構成されています。
1. ステークホルダー資本主義への移行
従来の株主資本主義(Shareholder Capitalism)は、企業が株主の利益を最大化することに重きを置いてきました。
しかしWEFは、従業員・顧客・地域社会・環境などすべての“利害関係者(ステークホルダー)”の利益を重視する新たな資本主義へ移行すべきと主張します。
つまり、単なる「利益追求」から、「持続可能性と社会貢献を両立させる経済活動」へ変えていこうというものです。
一見素晴らしい理念に聞こえますが、批判的な視点からは次のような懸念も指摘されます。
企業に倫理的・政治的ミッションを持たせることで、価値観の押し付けや選択の制限が起きる可能性がある
ESG投資(環境・社会・ガバナンス)などの“新たな評価軸”が、逆に市場支配の道具となる恐れ
2. グリーン経済と持続可能性の推進
グレートリセットでは、「気候変動への対応」と「持続可能な経済成長」が不可欠とされています。
具体的には以下の内容が掲げられています。
炭素税の導入
再生可能エネルギー(太陽光・風力)へのシフト
ガソリン車から電気自動車への移行
食料システムの再構築(例:昆虫食・合成肉など)
これらの施策は、「脱炭素社会」を作るために必要とされています。
しかし現実には、これらの改革が進むことで
既存産業の衰退や雇用の喪失
中小企業や農家の淘汰
一部のテック・エネルギー企業による市場支配
など、グリーン革命の名のもとに経済的格差が拡大するリスクも存在します。
3. テクノロジーによる社会の最適化と“未来型管理社会”
グレートリセットは、AI、IoT、ビッグデータ、ブロックチェーン、デジタル通貨(CBDC)などの技術を活用し、「より効率的で安全な社会」を実現することも目指しています。
例
個人の健康・行動を追跡するスマートヘルス管理
ワクチンパスポートやデジタルIDによる本人確認
中央銀行デジタル通貨(CBDC)による通貨管理
スマートシティにおける都市の自動制御化
こうした技術の発展は一方で、政府やグローバル企業が人々の行動や資産を“監視・制限”するツールにもなり得るという懸念も根強くあります。
「理想」は、誰にとっての理想か?
グレートリセットが描く未来は、「持続可能で平等な社会」とされています。
しかし、誰が設計し、誰の価値観で判断され、誰が利益を得るのか?という視点を抜きに、この構想を受け入れるのは危険です。
特に一般市民にとっては、「便利」や「安全」と引き換えに、個人の自由・選択権・所有権が縮小される可能性を十分に考慮する必要があります。
スポンサーリンク
第3章:なぜ批判されているのか?危険視されるポイント

グレートリセットは、一見すると「持続可能な社会」や「公平な経済」といった前向きなビジョンに見えます。
しかし、世界中で多くの識者や市民がこの構想に対して強い懸念や批判の声を上げています。
ここでは、グレートリセットがなぜ「危険」とされるのか、主な論点を整理していきます。
1. 「何も所有しない社会」は本当に自由なのか?
WEFが掲げた未来ビジョンのひとつに、以下のようなスローガンがあります。
「You’ll own nothing, and you’ll be happy.」
(あなたは何も所有しないが、それでも幸せである)
これは「シェアリングエコノミー」や「サブスクリプション経済」の延長線にある価値観とも言えます。
一見スマートで合理的な社会のように思えますが、批判的視点では以下のような問題が指摘されます。
土地や住宅、資産を個人が所有できない社会では、“自由”や“自己決定権”が失われる
所有を否定する構造は、結果的に“大企業や国家だけが支配する社会”を生む
人々が“借りる・使わせてもらう”ことで依存性が高まり、支配が容易になる
実際、テクノロジー企業による“使用許可”型サービスが拡大している現代では、ソフトウェア、音楽、動画、車、自転車などもすでに「所有」から「利用」へと変化しています。
2. パンデミックや危機を“好機”と見なす姿勢
クラウス・シュワブ氏は著書『COVID-19: The Great Reset』の中でこう述べています。
「パンデミックは、これまでの経済システムの限界を明らかにした。今こそ新しい社会を構築するチャンスだ。」
これに対しては、以下のような批判が起こっています。
危機の最中に「再設計」を提案するのは“意図的な誘導”に見える
パンデミック対策が市民の行動・自由・移動の制限を正当化する手段として使われた可能性
政府とテクノロジー企業が人々を“追跡”する新たな管理モデルを確立する機会となった
このような流れに対して、「恐怖を利用して社会を操作する構造」への強い疑念が広がりました。
3. “誰が設計するのか”という民主性の欠如
グレートリセットの構想は、国民や議会が議論した結果として生まれたものではありません。
それを提案しているのは、ごく一部のエリート層(WEFメンバー)であり、彼らは選挙で選ばれた存在ではありません。
■ 問題の本質:構想の規模は民主的なのに、決定は非民主的に行われている
この構造が続けば、「表現だけが民主的で、中身は支配的」という社会」に突き進む可能性があります。
特に、テクノロジーと金融が結びついた統治モデルは、「効率」と引き換えに「監視と管理」が進む懸念があるのです。
第4章:グレートリセットとアジェンダ2030の関係

グレートリセットを深く理解するうえで避けて通れないのが、国連の「アジェンダ2030」との関係です。
この2つは密接にリンクしており、“地球規模で進行する社会構造の再編”という共通のビジョンを持っています。
アジェンダ2030とは?
「アジェンダ2030」は、2015年に国連で採択された国際目標で、17の「持続可能な開発目標(SDGs)」で構成されています。
例
貧困をなくそう
質の高い教育をみんなに
エネルギーをみんなに そしてクリーンに
住み続けられるまちづくりを
気候変動に具体的な対策を など
これらは世界中の政府・企業・市民に推奨されており、学校教育やビジネス現場でも広く使われています。
グレートリセットとSDGsの融合的ビジョン
WEFは公式に「グレートリセットはアジェンダ2030と歩調を合わせるべき」と表明しており、以下のような点でSDGsと連動しています。
| SDGsの目標 | グレートリセットでの対応 |
|---|---|
| 貧困の撲滅 | ベーシックインカム導入・所得再分配 |
| クリーンエネルギー | 再エネ・脱炭素・EV政策 |
| 持続可能な都市 | スマートシティ・監視型都市設計 |
| 働きがいと経済成長 | ステークホルダー資本主義・ESG評価 |
| 健康と福祉 | ヘルステック導入・医療の自動化 |
つまりSDGsの目標は、「理想的な未来のための共通言語」として機能しつつ、グレートリセットの実装を正当化するフレームになっているとも言えます。
本来の“善意”が、操作の道具になり得る
SDGsやアジェンダ2030は、世界をよりよくしようという理念から出発しています。
しかし、それが透明性の低いグローバル機関や企業の“管理のためのツール”になってしまえば、善意が逆に利用されることになります。
■ 問題点:理想の共有が、「従わない者を排除する構造」を生み出すこと。
- 「気候変動に協力しない人は非国民」
- 「ワクチンを受けない人は差別対象」
- 「マイナンバーを使わないと不便にする」
こうした動きは、すでに現実になり始めています。
第5章:日本への影響は?──見えないかたちで進行する構造改革

「グレートリセットは海外の話」と思っている方も多いかもしれません。
しかし実際には、その影響はすでに日本国内の法制度・インフラ・日常生活の中に入り込み始めています。
ここでは、「静かに進行する変化」に焦点をあて、日本社会が直面している実例を取り上げます。
1. 種子法の廃止と食料の“コントロール”
2018年、日本で主要農作物種子法(通称:種子法)が廃止されました。
これは、コメ・麦・大豆などの安定生産・地方保護を目的に、国や自治体が種子を管理・提供していた法律です。
廃止によって以下のことが起こっています。
種子の管理が民間(外資を含む)に開放
地方農家は大企業の特許品種に依存
種子ビジネスに参入する多国籍企業(モンサント等)の影響力が増大
これは、食料の“所有”と“供給権”が国から企業へ移行した事例とも言えます。
2. 水道法改正と民営化のリスク
2018年の水道法改正により、水道事業の運営を民間企業に委託できる「コンセッション方式」が導入されました。
表向きには「老朽化した水道インフラの再整備」や「財政負担の軽減」が目的とされます。
しかし現実には
水道料金の上昇(海外事例では2〜3倍になったケースも)
外資系企業が自治体と契約を結び“命の水”を管理
運営の不透明化や災害時対応への不安
- 水の品質悪化は避けられない可能性
など、「公共性の高い資源のコントロールが企業側に移る」ことへの懸念が広がっています。
3. デジタル庁とマイナンバーの“超管理社会”化
2021年に発足したデジタル庁は、行政サービスの効率化やIT化の推進を目的としています。
その中心にあるのが「マイナンバーの全面活用」と「デジタルIDの統合管理」です。
進行中の主な施策
健康保険証とマイナンバーの統合(マイナ保険証)
銀行口座との紐付け
ワクチン接種証明・医療履歴との統合管理
将来的には納税・年金・運転免許証なども統一の可能性
一見便利に見えますが、個人情報の中央集権化はプライバシーの脆弱化や国家による“行動制御”の土台となり得ます。
4. 経済・雇用への構造転換と「個人事業化」社会
グレートリセットでは、正社員という雇用形態が縮小し、「フリーランス」「ギグワーカー」「副業」など、柔軟だが不安定な働き方の普及が推奨されます。
日本でもすでに始まっていますよね。
雇用の流動化(終身雇用の解体)
年金制度の持続性への疑念
非正規雇用・副業推進の流れ
教育現場における「アントレプレナーシップ(起業精神)」教育の導入
といった動きが進んでいます。
一見“自由な働き方”ですが、裏を返せば「自己責任の名の下に、国や企業のセーフティネットが弱体化する社会」とも言えます。
これらの変化はすべて、グレートリセットの本質と呼応しています。
「効率化」「持続可能性」「自由」「多様性」といった言葉の裏に、本当に守られるべきもの(個人の権利・生活の基盤・民主的プロセス)が失われてはいないか?
この視点を持ち続けることが、これからの日本人にとって重要です。
第6章:グレートアウェイクニング──対抗概念としての“目覚め”

グレートリセットに対して、もう一つの言葉が静かに広がっています。
それが 「グレートアウェイクニング(Great Awakening)」=“人々の目覚め” です。
「目覚める」とは何を意味するのか?
ここでいう「目覚め」は、単に陰謀論を信じることでも、政府を敵視することでもありません。
それは、情報の裏を読み、自らの頭で考え、主体的に選択できる人になることです。
グレートリセットが世界のルールを「上から」再構築する動きだとすれば、グレートアウェイクニングは、世界の真実に「下から」気づき、草の根で変革を起こそうとする力です。
グレートアウェイクニングが重視する価値
個人の主権と自由
あらゆる監視や強制に対して「選ばされるのではなく、自分で選ぶ」ことを守る。ローカルの復権
地産地消、地域経済、顔の見えるつながりを大切にする。グローバル依存からの脱却。情報リテラシーの強化
SNS・テレビ・専門家の意見に流されず、事実を調べて咀嚼する力。精神性と共同体の回復
物質的な豊かさだけでなく、人と人との信頼・直感・誠実さといった“目に見えない価値”を取り戻す。
日本にとっての“目覚め”の意味
日本は、世界の中でも特に「同調圧力」「事なかれ主義」「空気に従う文化」が根強い国です。
そのため、支配構造が可視化されにくく、従順に受け入れやすい土壌があります。
しかし、今の時代だからこそ、気づいた人から動くことが重要です。
自分の生活を守るために、情報の受け手ではなく“読み解く人”になる
子どもたちに残す社会の在り方を、他人任せにしない
「どうせ変わらない」ではなく、「まず自分の半径1メートルから」意識を変える
小さな目覚めが、やがて大きなうねりとなり、「支配される社会」から「選択できる社会」へと流れを変える力になっていきます。
【結び】リセットではなく、覚醒の選択を
グレートリセットは、確かに壮大で、美しい言葉で彩られた未来図を提示しています。
しかし、その裏にある“誰のための設計か”という問いから目を背けるわけにはいきません。
「私たちは本当に、自分たちの未来を選んでいるのか?」
その問いに気づき、考え、行動する人が増えることこそが、グレートアウェイクニング=真の目覚めの始まりなのです。
多くの方が世界の仕組みに気づき、意識が変わることを願います。
あわせて読みたい
この記事のPart.4はこちら